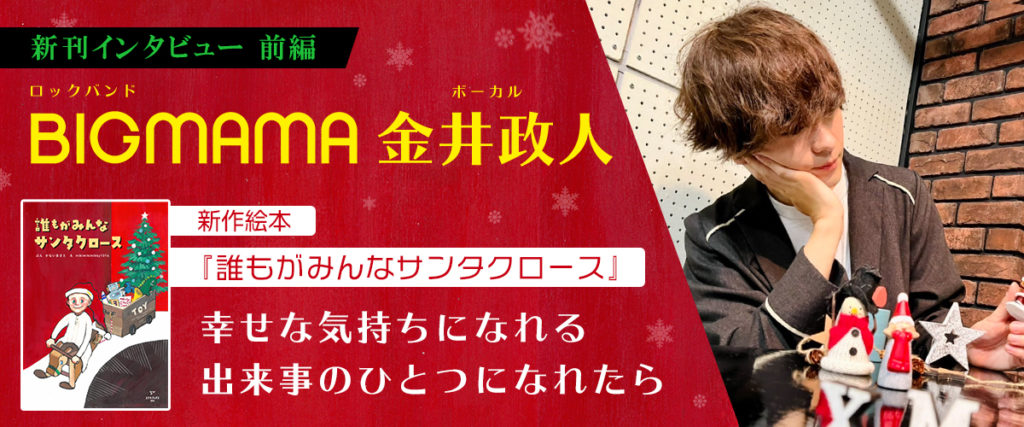2004年の結成以来、4度にわたり『キングオブコント』のファイナリストとなるなど、注目を集め続けるコントユニット「THE GEESE(ザ・ギース)」。テレビ・ライブ等で活躍する、ザ・ギース・高佐一慈(たかさ・くにやす)さんが、新たに文芸の世界にも活動の場を広げます!
3月3日に刊行されるはじめての短編小説集『かなしみの向こう側』(ステキブックス)は、THE GEESEだけでは表現しきれなかった高佐さんの内なる世界を垣間見せてくれる1冊です。
「ナニヨモ」では、今回の出版のきっかけを作った小説家・中村航さんによる高佐さんへのインタビューを敢行し、さらなる内面を探ってみたいと思います!!
(聞き手・中村航)
この記事は全3回の【中編】です。
【前編】はこちらよりお読みいただけます。

1か月、ひと文字も書けなかったんですよ
中村航(以下・中村):そして小説も書いてみよう、と。最初は、どんな感じでしたか?
高佐一慈(以下・高佐):だから書いたことなんてまったくないですし、そもそも作文も苦手だし……、読むのは好きだったんですけど……。でもせっかくお話をいただいて、目をかけてもらったことが嬉しくて、「じゃあちょっと、ご期待に沿えるかわかりませんけど」って、なんか火が点いたっていう感じはありますね。
中村:それはよかったです。僕もちょっと覚えてるんですけど、大竹マネージャーが「エッセイとかの依頼はこれからもあるだろうけれど、小説の依頼はこれが最後かもしれないから書いちゃいなよー」って、わりとノリノリだったような記憶があります。
高佐:ああ、そうだったかもしれないですね。うんうん。
中村:エッセイを書かれていることは知っていたし、コントを書かれているっていうのもあるし。気軽に、短いものでもいいので、なにかひとつ書いてみたらどうですかってお話をして。
高佐:はい、覚えてます。2020年の12月です。
中村:そうしたら、しばらく経ったらその小説が送られてきて……。
高佐:いやいや、ちょっと違いますよ(笑)。最初にお話があってすぐ「じゃあ……」って取り組んでから1か月、ひと文字も書けなかったんですよ、僕!
中村:すぐ書こうとしてくれてたんですか。
高佐:もちろんです。その日からいろいろ、設定とか案とか、他の小説を読んだりしながらず~っと……「あ、ちょっとこれで書いてみよう」って、PCを起ち上げてキーボードに指までかけるんですけど、もうひと文字も書けなくって、そこから2021年までの年末年始とかは、もうずっと「どうしよう!?」っていうのでいっぱいだった気がします。
中村:でもコントだったら書けるし、エッセイも書けるわけですよね。どうして小説はそんなに、書けなかったわけですか?
高佐:あの……僕、思ったんですけど……こんなこと言っていいのかわからないんですけど、どうしても書きたいって思えるものがなかったんですよ。
中村:ああ、はい。
高佐:僕が勝手にイメージしていた小説家の方っていうのは、「こういうものが描きたいっていう思いがあって、そのエネルギーを原稿用紙とかPCにぶつけてるんだろうなあ」っていうものだったんで、その情熱が、「どうしてもこれが書きたい」っていうのがないのに書けないよって思っちゃったんですよ。それで1か月経って、「ああ、中村さんに連絡しなきゃなあ」って思いつつ、1月1週が終わり2週が終わり、3週終わったくらいで「その後どうですか?」っていうLINEが来て……(笑)。
中村:嫌なLINEですねえ(笑)。
高佐:これはもう自白するしかないってなって、「すいません。ひと文字も書けてません」って言って、もういちど打ち合わせさせていただいた、という。
中村:すごくわかるんですけど、僕も書きたいものとか別になかったんですよ。小説を書き始めたころ、よく考えたんだけど、書きたいものって考えたらほんとにひとつも浮かばなかったですねえ。
高佐:ええ~!?
中村:書くべきものっていうのは浮かんだんですけど。書くべきものと、「こういうのなら書けるかもしれないな」っていうのがぼんやり浮かんで、じゃあその書けそうなものを書いてみようかっていうのが最初ですね。
高佐:ああ、じゃあそれと一緒かもしれません。
中村:うん。「書きたい!」っていう体は、どこかで取りますし、実際書きたいことを書いてるんですけど……。だから2種類いるかもしれません。作家同士でよく言うのは、「無人島行っても小説を書くか?」っていうので、「書く」って言う人がいるんですよね。「いや、書かないよ!」って僕は思うんですけど。自分のために書くのと、他人のために書くというのの、バランスがあるんだと思います。
高佐:ああ……。
中村:で、作家でも、書かない人のほうが多いと思います。多いっていうか、ほとんどだと思うなあ。
高佐:ああ、そうなんですか。
中村:ただ、無人島行っても書くって人も、何人か知ってます。
高佐:僕はだから、無人島行っても「書く」っていう人しかいないと思っていたんで。
中村:いや僕は、無人島では1行たりとも書かないですね(笑)。無人島行っても、っていうのは「誰も読む人がいない世界」ってことですけど。
高佐:はいはいはい。
中村:高佐さんは、たとえば、「気軽に書いてみたらどうですか?」っていうような話をすると、いきなり難しい顔をされましたね。
高佐:すぐ顔に出ちゃいます、はい。
中村:でも、こんなのはどうですか? っていう問いかけには、「あ、じゃあ……」って感じに、アイデアはポンポンと返ってきて……。
高佐:そうでしたっけ?
中村:遠い記憶を探るようだったり……。今回の表題作の「かなしみの向こう側」もそうなんですけど、「昔こういうコントをやったことがあるんですけど」って出てきて、「それはめちゃめちゃおもしろそうじゃないですか!」って。別に励ましで言ってたわけじゃなくて、それ読みたいと思って言ってただけなんですけどねえ(笑)。
高佐:「頭の中で全部出来上がっちゃったら書けないんだ」とかフォローしてくれたことを覚えてるんですけど。
中村:ああ。頭の中で完成していると、そこが完成形であって理想であって、書けばかくほどダメなものができていく、っていう話ですね。
高佐:あと「なんでもいいから1行目を書き出したら、そこから書けることもありますよ」とか。その言葉を胸の引き出しにしまって、持ち帰って、それで書き出したのを覚えてます。
中村:ほお。そうしたら1作目ができたってことですよね。
高佐:1作目が、はい。もちろんそのお話ししに行ったときに、「こういうのとかどうですか?」って言って、「ああ、それめっちゃいいじゃないですか」って言ってもらえたのも励みになって、それプラス「とりあえずなにか書き出す」っていう、「全然、いいものじゃなくていいから」って思って、書きはじめたのがあれですね。

1個設定が出たらそこから大喜利的に
中村:「旅をするような話を書きたい」って最初言われてたのと、「コンタクトレンズ」(収録作品「天然コンタクトレンズを巡る旅」)のアイデアは結構最初から言われてましたよね。
高佐:そうですね、たぶん打ち合わせしているときに、中村さんが眼鏡かけてらっしゃって僕はコンタクトなんで、「たとえば“コンタクトを探しに行く”」って言って、「それいいじゃないですか!」ってなったんで、もう「この設定だとああなってこうなって、上手くいかないかなあ?」って考えはじめると元の木阿弥になっちゃうんで、これでいいからとりあえず書こうと思って。
中村:最初に読んだとき、ちょっと小ガッツポーズしちゃいました(笑)。
高佐:ああ、そうですか。ホッとしていただけたんですか、それは?
中村:まず小説の体をちゃんと成してたし、題材もアイデアがあっておもしろいし、短編としてまとまっていて。すごく嬉しくて「よっしゃ、行けるぜ!!」っていう風に思ったのを覚えてます。
高佐:いやあそんな、まさかそんな風に思っていただけてるとは思ってなかったです。
中村:それなのに「これでいいんですか?」とか弱気なことををおっしゃってるので、「それはあとで考えて」って、次のを書きましょうっていう風に進めていきましたよね。
高佐:そうですね、はい。
中村:その頃、「どういう風に、こんなおもしろいことを書いたんですか?」って聞いたら、「大喜利をする」って言われていて、画期的だと思ったんです。
高佐:いやその、書き方がわからなかったので。もちろんはじめてですし、他の方がどうやって書いてるのかまったく知らなかったので。コントを考えるときは、1個設定が出たらそこから大喜利的に、「こんなのもあるかな、こういうのもあるかな」とかって書き出していってるんで、それと同じやり方っていうか。
中村:ひとつのテーマについて……。
高佐:そうですね、はい。「こういうボケがあるかな?」みたいな。コンタクトレンズのヤツは結構楽しかったんですよ、その作業が。「こんなのがあるな。あ、こんなのもあるな」っていうのがあらかた出たところで、じゃあちょっと書きはじめてみようってなって……。
中村:テーマがあって、それをブレインストーミングしてアイデアを出していくっていうやり方があるんですけど、それが高佐さんにとっては大喜利ってことなんですかね?
高佐:たぶんそうだと思います。そのコンタクトレンズの設定でも、「これは実際には入れられないだろうな」っていうのも別に関係なく、とりあえず「出すだけ出して」みたいな。たしかにブレインストーミングと似ているかもしれないですね。
中村:論理的なアイデアより、出すだけ出したアイデアのほうが、おもしろそうだったりするってことですよね?
高佐:そうですね、「ボケがいっぱい眠ってるんだろうなあ」とか。
中村:突飛なアイデアってことですもんねえ。まず「天然コンタクトレンズ」ってなんだよってことですもんね。で、「こんな天然コンタクトレンズは嫌だ」じゃないですけど……。
高佐:……みたいなことですね、はい。「丸い玉の中に入ってる」「貝みたいな感じで獲れる」とか「小夢宅村(こむたくむら)っていうところで最初に発見された」とか「日本ではそういう漁場が他にもあと2つある」とか。
中村:これはすごい話ですよ!
高佐:そうですかね? なんか普通のネタ出しみたいなことだと思うんですけど(笑)。
中村:まずその大喜利って……たとえばコピーライティングとかタイトルを考えるときとか、同じような考え方でやってたりするんですけど。そういうのって「鍛えればすごくアイデアが出るようになる」って聞いたことがあるんですけど……。
高佐:たぶんそうですね。筋トレと似てると思います。なんか大喜利って、もちろんもともとセンスとか才能を持ってる方もいるんですけど、努力で向上していく感じがあるんで、そういう意味で、ピアノだったりハープだったりをコツコツやっていくのが好きっていうところにつながっているのかもしれませんね。
中村:ほんとにすごいなあって思うんですよね。番組とかイベントで芸人さんが大喜利やられているのを見て、ときどきこっそり、自主的に参加してみたりするんですよ。でもやっぱりスピードもクォリティも全然追いつかなくて。やっぱりそういう訓練とか場数とかがあってできる「能力」ですよね。
高佐:いやあ、僕もこんなふうに言ってますけど、別に「じゃあ、おもしろいのか」って言われたら……おもしろくないことも多いんで(笑)。
中村:いや、そんなことないですよ(笑)。高佐さんはちょっと……普通にしてても特徴があるというか(笑)。若林正恭さんが「上品な狂気」(書籍推薦文)っていう風に書いてくれたんですけど、確かに高佐さんってすごく謙虚な方で……。
高佐:(笑)。いや、謙虚にしてる体を取ってるだけなんですけど。
中村:確かに謙虚にしていても……狂気を感じさせる(笑)。
高佐:ああ、よく「笑顔のままでなんの躊躇もなく人を刺しそうだよね」みたいなことは言われます(笑)。
中村:上品に人を刺すんですかね(笑)。大喜利の色もすごく際立ってますよね。
高佐:ええ~!? そう言っていただけたら嬉しいですけど。
中村:その上品な狂気で、大喜利されながら書いたっていうことなんですけど、その思考法って言うんですかね……。まず自分の中で問いを立てる能力っていうのも必要だと思うんですけど。お題を考えるのと、それに対して自分で考えていくっていう、この繰り返しで人ってものを考えていくんですけど、それをトレーニングしたりふだんからやられてる方が、その公式を意識しながらものづくりに挑むと、「ああ、おもしろい小説ができるんだなあ」っていうのが、すごく今回思ったことですね。
高佐:いやあ、ありがとうございます。嬉しいです。ほんとにもう「おもしろい」って言ってもらえるだけで満足というか、もう本当にありがとうございますっていう……。
中村:「大喜利思考法」「大喜利クリエイティブ」みたいな……。大喜利できる人は、みんななんでもできそうですね。
高佐:どうなんですかね。でもまあ、重要な部分は担ってると思います。その大喜利の力は。
中村:大喜利って方法を意識して創る、ってのが、高佐さんって方法的というか、ざっくり言ってしまうと理系的っていうか、システマチックな考え方でものを作られているんだなって思いました。
高佐さん:でももう、それしかやり方がわからなかったからっていうことです。
非日常的な、不穏な空気が漂うものが好きなので
中村:短編を5作書いてもらって、最後に順番をどうしようかなあっていろいろ考えたり相談したりしたんですけど、ほぼ書かれた順番ですよね。
高佐:ほとんどそうですね。2番目と3番目を逆にしたくらいで。
中村:それぞれなにか、書き方が変わったり気持ちが変わったりとかしたんですか?
高佐:とにかくはじめてなんで、最初に「天然コンタクトレンズを巡る旅」を書いたときに、三人称の主人公視点だったじゃないですか。それで中村さんには「その感じがいいかもしれませんね」っておっしゃっていただいたんですけど、自分の中ではなにが正解でなにが悪っていうのがわからなかったんですね。で、最初が男性の主人公だったんで、2作目(収録は3作目)は三人称の女性主人公にして、3作目(収録は2作目)が一人称の女性主人公で、4作目は一人称の男性主人公にして……っていう風に、自分の中では書き方というか、いろいろ試してみたっていう感じです。
中村:人称を変えたことで、なにか変わりましたか?
高佐:一人称の「僕」、男性って言ったら、やっぱり自分じゃないですか。なんかそのほうが、グッと入り込んでいく感じが強かったっていうか……。どの小説にも実際に体験したことが入っていて、最初に「書けない」って相談に行ったときに、「自分が体験した現実のことを書くと、物語の強度も増すし、書きやすいのでいいですよ」って言ってもらったからで。たしかに「天然コンタクト~」の冒頭の部分は、よく経験してる自分のことを書いたんですよ。そうしたら、すらすら書けたので。どれも自分の過去の記憶とか経験からのものと、虚構の部分を一緒に合わせて書いた、みたいなところがあります。
中村:自信を持って書けるんですよね、本当にあったことだと。「こんなこと書いていいのかな」とか「こんなときこんな気持ちになるかな」とか、嘘かほんとかわからなくても、「いやいやこれは本当のことだから」って思えば書けるので、それを「強度が増す」って言ったんです。
高佐:ああ、なるほど。
中村:独特な、ちょっと変わった世界観を持った作品にしようっていうのは、意識されました?
高佐:そうですね、やっぱり非日常的な、不穏な空気が漂うものが好きなので。
中村:僕も、おそらくそういう感じになるんだろうなっていう風には、特に「天然コンタクト~」とか最初はそう思ってたんですね。でもなんか、読みはじめたとき、すごく入り方が日常的で、普通の世界にいながらも、なんか「あれ?」っていうような、切り替わる瞬間がどの小説にもありましたよね。
高佐:ああ、そうですね。全部そうですね、日常から入って、徐々にこう……。いや、ほんとに若林さんにいただいたコメントがまさにそうなんですけど、そこからどうやって非日常に移行していこうかなっていうのは、全部考えました。
中村:なんか、まだらになってるところとか……それこそ海と湖が混ざってる……。
高佐:ああ、汽水湖(きすいこ)。
中村:そうそう。「これはどっちなんだ!?」みたいなところもあっておもしろかったですね。第1作を読むと「あ、こういう構造なのか」みたいなのがわかって、どこかに「境」があるんだなとか。最初から汽水域みたいな小説もあるじゃないですか。「玉依存」とか。まあ日常から入ってはいるんですけど、「どっちなんだ」っていうのが最後までわからなくて。いろいろお笑いとの違いとかも考えながら読んでたんですけど、おもしろかったですね。「変な世界なのに、いつまで経っても、誰もツッコまない」っていうのが、読者としては……「俺がツッコまなきゃいけないのか!?」みたいな。
高佐:(笑)。ああ、そういうのは好きかもしれないです。
中村:読んでいておもしろかったですね。そのへんはもう、読者を信用しないとできないので、見事だなと思いました。
(写真:吉田明広 照明:中村航)
高佐一慈(たかさ くにやす)プロフィール
1980年、北海道・函館市出身。2004年3月、尾関高文とともにお笑いコンビ「THE GEESE」(ザ・ギース)を結成。コントを基盤とし、多岐にわたって活動中。キングオブコント2008・2015・2018・2020ファイナリスト。特技はパントマイム、ハープ。
■THE GEESEオフィシャルHP|https://thegeese.jp/
高佐一慈さんの『かなしみの向こう側』【限定サイン本】を「ステキブックス オンラインストア」にて販売中です! この機会に、ぜひお買い求めください!
Amazonでのご購入はこちら

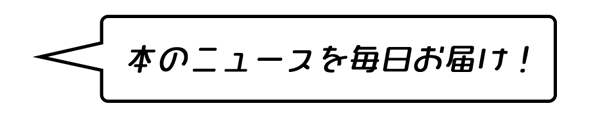




-88x88.jpg)