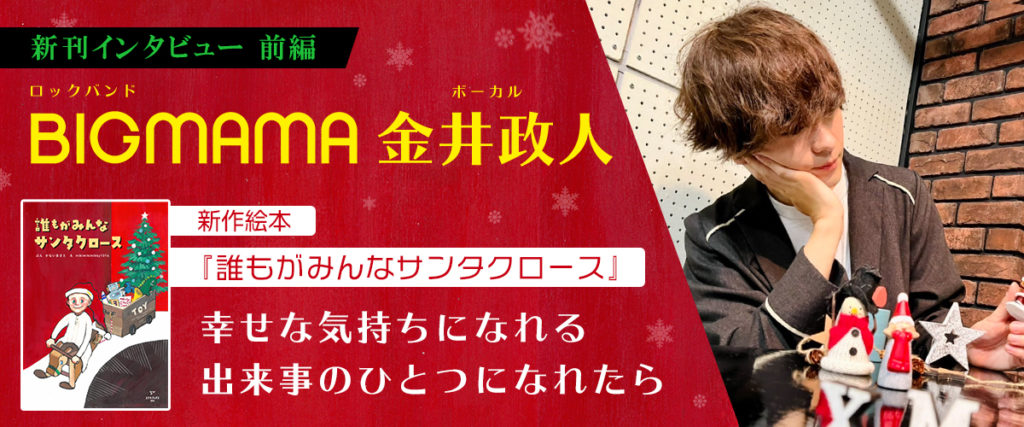「地球を貫く穴を掘って、日本−ブラジル間・直線ルートを造る」――壮大なファンタジーのようなその極秘の国家事業に、生真面目に向き合うサラリーマンを描いた『いつか深い穴に落ちるまで』で2018年にデビューした山野辺太郎さんが、待望の新刊『孤島の飛来人』を8月22日に刊行します。
風船を背負って空へ飛び立ち、たどり着いた先には誰にも知られていなかった「歴史」が待っていた――デビュー作と同様、読み手の想像力をかき立て、小説読書の醍醐味を味わわせてくれるこの作品について、山野辺さんにお話を伺いました。

働く日々の実感をふまえて書きました
――『孤島の飛来人』について、これから読む方へ、内容をお教えいただけますでしょうか。
主人公の「僕」は自動車メーカーに勤める若手社員です。遠い将来を見すえて、個人で使える飛行器具の開発に携わっていました。その会社がフランス企業の傘下に入ることになって、自分たちの研究など不採算部門として切り捨てられるのではないか、という懸念が持ち上がります。ならば急いで結果を出そうということになり、「僕」は横浜のビルの屋上から、六つの大きな風船にぶら下がって飛び立ちます。目指していたのは、小笠原諸島の父島でした。
そのあとどうなったかは、ぜひ小説を読んでみてください。作者である僕も会社勤めをしておりまして、働く日々の実感をふまえて書きました。
――本作を描こうとされたきっかけを教えていただけますでしょうか。
かつて、風船おじさんと呼ばれた人物がいました。ピアノ調律師の鈴木嘉和さんというかたです。彼はビニール製の巨大な風船をいくつもくくりつけた木製のゴンドラを作って、ファンタジー号と名づけます。これでアメリカまで飛行しようともくろんで、実際に飛び立ちました。一九九二年十一月二十三日のことで、当時僕は高校二年生でした。彼は琵琶湖畔から出発して、翌々日には宮城県沖の東方約八百キロの洋上を飛行中の姿が確認されていますが、その後、消息を絶ちました。
ファンタジー号での飛行中、「明るくなってきた! スバラシイ朝焼けだ!」という感嘆の声を、彼は携帯電話で妻に伝えています。そのことは、妻による手記『風船おじさんの調律』(石塚由紀子著、未來社)に記されています。
彼のとった行動は、自らの命をなげうつような振る舞いにも見えますが、そこには陰鬱さや悲愴感よりも、奇妙な情念の光と熱気が、ほのかに明るく暖かく、残りつづけているように思うのです。少なくとも、僕の胸のうちには残っていました。
小説を書くことも、読むことも、ある種の旅であり、ときには冒険でもある
――ご執筆にあたって、苦労されたことや、当初の構想から変わった部分など、執筆時のエピソードをお聞かせください。
当初、北海道のまんなかの大雪山のあたりから、北東の知床半島を目指して飛び立って、そのさきの細長い島にたどり着いてしまったとしたらどうだろうか、と考えました。極寒の地での囚われの日々は相当に過酷なものになるだろう、とひるむ気持ちがありました。むしろ暖かい土地に向かってはどうか、と考え直して地図帳を眺めていたところ、小笠原諸島の父島や母島、さらには北硫黄島、硫黄島、南硫黄島と並んだ島々が目に留まりました。そこから小説の舞台が見えてきたのです。
とくに心惹かれたのが北硫黄島です。太平洋戦争の激戦地となった硫黄島に比べて、あまり知られていない島ですが、十九世紀の末から戦争末期までの約半世紀にわたって、人々が暮らしを営んでいました。最盛期には二百人以上、最終的には九十人ほど住民がいましたが、戦禍を避けるため、本土への強制疎開が実施されました。その後、元住民がふたたびこの島に戻って暮らすことはかなわず、現在に至るまで無人島となっています。
故郷を追われ、帰ることのできない人々のいだいたであろう無念さに、思いを馳せました。小説のなかだったら、いまも人々の暮らす北硫黄島を描けるのではないか、という考えが浮かんできます。そこには現実の歴史とは別の、もう一つの歴史が隠れている、と想定してはどうか。硫黄島の戦いの場から船で逃れた将兵が、北硫黄島にたどり着いて住民と合流し、いつしか国をつくっていたとしたら……と想像がふくらんでいきました。
「孤島の飛来人」という小説を書いたことで、僕自身のなかで現実の島々への関心が高まり、関連する本を読んだり、船旅で小笠原諸島を訪ねたりしました。そのときの経験をもとに「孤島をめぐる本と旅」という短篇を書き、本書に収録しました。この短篇のなかで取り上げた本でもありますが、『硫黄島』(石原俊著、中公新書)からは、現実の硫黄島や北硫黄島を知るうえで貴重な示唆を得ました。
――どのような方にオススメの作品でしょうか? また、本作の読みどころも教えてください。
風船にぶら下がってビルの屋上から飛び立ちたいけれど、なかなか一歩が踏み出せないかた。もしいらっしゃいましたら、この本をぜひどうぞ。小説を書くことも、読むことも、ある種の旅であり、ときには冒険でもあると思っています。
「孤島の飛来人」では、北硫黄島の歴史を虚実取り混ぜて描いています。この小説を読んで現実の島々に興味をもっていただいたなら、「孤島をめぐる本と旅」を手がかりに、ノンフィクションの本を手に取ったり船旅に出たりするのもおすすめです。
おがさわら丸の船内の売店で買った『しまの音 〜紡ぐ〜』(歌・okei)というCDには、小笠原諸島にまつわる歌が収められていて、旅から帰ってよく聴いていました。ゆったりとしたメロディーにひたっていると、島の情景が心に浮かんできます。
書くことを通して未知の世界に踏み込んでいき、何かを見つけ、何者かと出会いたい
――小説を書くうえで、いちばん大切にされていることをお教えください。
書いてみないとわからないものを書きたい、と思っています。言い換えれば、自分がすでに知っていることを書くというより、書くことを通して未知の世界に踏み込んでいき、何かを見つけ、何者かと出会いたい、という思いがあります。
そうはいっても、まったく知らないことでは書こうと思いつくことすらできません。少しだけ知っていて、もっと知りたいと心を動かされたことについて、現実の輪郭をつかむだけでなく、そこにひそんでいる可能性を探ってみようとして書いているような気がします。
――最後に読者に向けて、メッセージをお願いします。
小説というものは、作者が書き終えただけではまだ本当にはできあがっておらず、読み進めていく読者の心のうちでその都度、できあがっていくのだと思っています。その意味で、本をひらいて作品世界を繰り広げてくださる読者の皆さまの想像力に、感謝したいと思います。ありがとうございます。本書を読むことが、いくらかなりともよき旅の経験となりましたら何よりです。
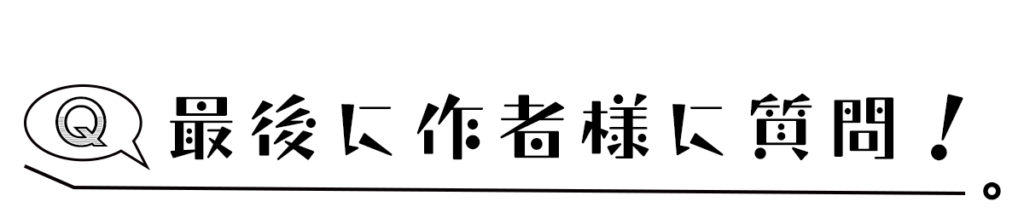
Q:最近、嬉しかったこと、と言えばなんでしょうか?
この本をつくることができたことです。デビュー作『いつか深い穴に落ちるまで』を刊行して以来、文芸誌での作品発表を続けてきました。次の単行本を出せるとよいなと思いながら、だいぶ時間が経ってしまいました。
そんななか、デビュー作で僕の小説に興味を持ってくださった編集者さんと、インターネットを介して知り合いました。メールでのやりとりを経て、お会いしてお話ししたところ、雑誌に発表していた「孤島の飛来人」を改稿し、書き下ろしの短篇を加えて本にしましょうという話がまとまって、実現の運びとなったのです。本当にうれしい出来事でした。
Q:ご自身は、どんな小説家だと思われますか?
学生時代からほそぼそと小説を書いていたのですが、デビューしたのは四十二歳のときでしたから、遅咲きといえるように思います。気持ちのうえではあせりを感じることもよくあるのですが、あがいたところで結果はゆっくりとしか出ないのだから、あわてずに息長く取り組んでいくしかないのだろうと観念しています。
また、少しばかり調子外れの事柄を描くときでも、なるべく落ち着いた言葉遣いで書こうと心がけています。そのあたりの内容と表現の釣り合い、あるいは不釣り合いに、もしかすると書き手としての色合いが出ているのかもしれないと感じます。
Q:おすすめの本を教えてください!
『アメリカ』フランツ・カフカ 中井正文訳(KADOKAWA)
『変身』『審判』『城』など、閉塞的で奇妙な状況のなかに投げ出されながらも自身の職務にひたむきに取り組もうとする人物を描いたカフカの作品群には、惹きつけられるものがあります。独文科の学生だったころよりも、勤め人になってからのほうが、読んでいて身につまされるようになりました。カフカの作品のなかでも『アメリカ』は、ほかとは少し風味が異なり、少年を主人公とした冒険的な旅の小説です。作者自身が訪れたことのない新天地アメリカが舞台となっています。『失踪者』というのが作者自身の考えていた題名だったようなのですが、刊行当初の題名『アメリカ』という言葉が喚起する広々とした感じも作品にふさわしく思えます。
『コルタサル短篇集 悪魔の涎・追い求める男 他八篇』フリオ・コルタサル 木村榮一訳(岩波書店)
ラテンアメリカ文学によくみられる、幻想と現実が不思議に混交した作品世界にも親しみを覚えてきました。ボルヘスやガルシア=マルケスといった作家が思い浮かびますが、ここではコルタサルの本を挙げたいと思います。この本に収められた「正午の島」は、飛行機の客室添乗員を務める男が、正午に機内の窓から見える島に魅了され、いつかあの島を訪れたいと願いつづけた果ての出来事を描いた話です。「南部高速道路」は、渋滞の極まった路上で車中生活を始めなければならなくなった人々が、いつ終わるとも知れない日々を過ごすなかで形づくっていった共同体の消息を追った短篇。驚異に満ちたさまざまな世界をかいま見ることのできる一冊です。
『ベスト・オブ・イヨネスコ 授業/犀』ウージェーヌ・イヨネスコ 安堂信也、木村光一 他訳(白水社)
劇作家イヨネスコの戯曲集です。戯曲ということではギリシャ悲劇やシェイクスピア、ブレヒトなども好んで読んだり上演を観たりしてきましたが、イヨネスコの作品にも独特の魅力を感じます。「犀」では、ある街で人が犀に変貌するという事態が起こります。人々は驚き、戸惑いますが、やがてあの人も、この人も、犀になっていきます。現実には、人間が犀になることはないのでしょうが、これと似たことを、人は生きていくなかで経験することがあるのかもしれません。自分は変わらないのに、まわりの人たちが何かに染まったように変わっていく。あるいは、自分もまた変わってしまう側の一人になるのか。そんなことに考えをめぐらしたくなります。
山野辺太郎さん最新作『孤島の飛来人』

発売:2022年08月22日 価格:1,760円(税込)
著者プロフィール

山野辺太郎(ヤマノベ・タロウ)
1975年、福島県生まれ。宮城県育ち。東京大学文学部独文科卒業、同大学院修士課程修了。2018年に「いつか深い穴に落ちるまで」で「第55回文藝賞」を受賞しデビュー。以降、文芸誌等で小説作品「孤島の飛来人」「こんとんの居場所」「恐竜時代が終わらない」や随筆を発表し現在に至る。

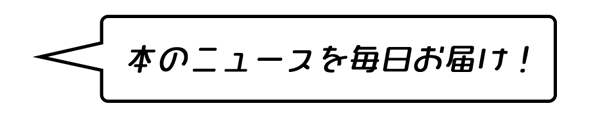




-88x88.jpg)