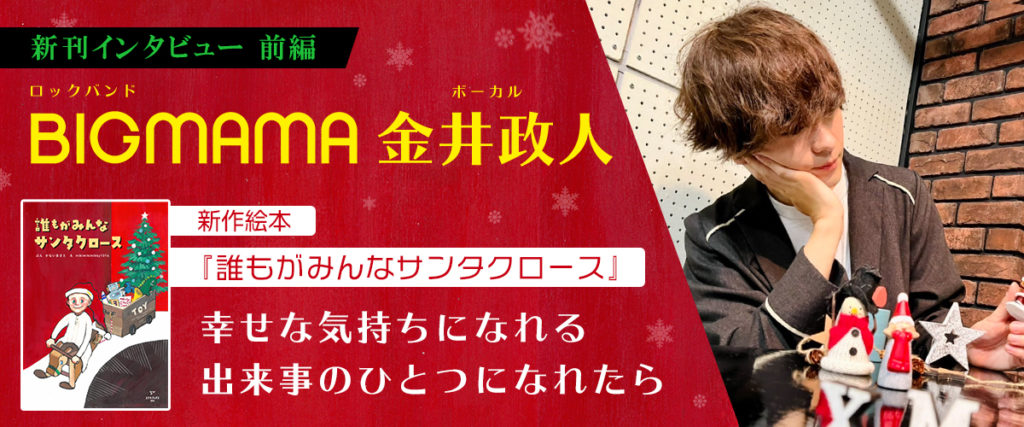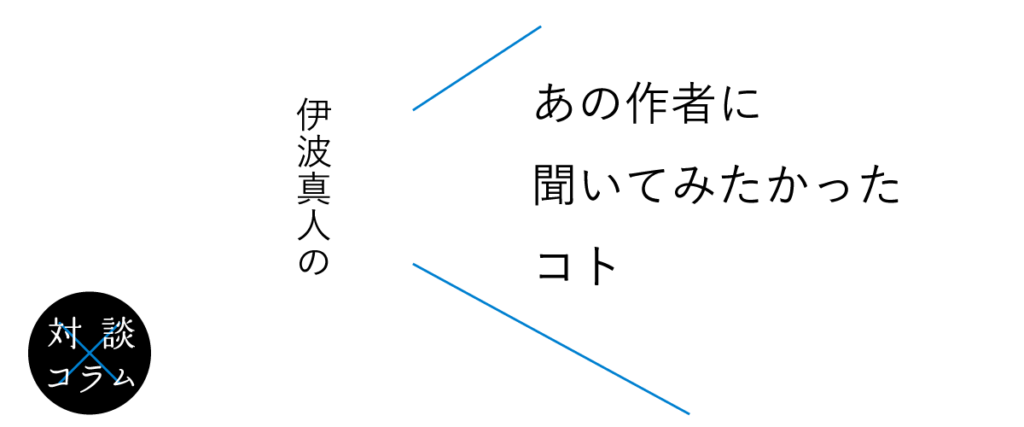
伊波真人が、毎回ゲストをお迎えして、聞いてみたいことを聞いてみる、この企画。
第5回のゲストは、以前から伊波との交流もある、角川学園小説大賞優秀賞を受賞された『“菜々子さん”の戯曲』の作者で、最近は児童文学なども手がけられている、小説家の高木敦史さんです。

伊波:高木さんとはもともとTwitterでつながっていて、二人ともKIRINJIが好きだったり、共通点が多くて気になっていました。最初にお会いしたきっかけは、何でしたっけ?
高木敦史(以下、高木):僕が講談社さんから本を出すことになって、誰かに帯を書いてもらおうというときに、「高木さん、誰かお知り合いの作家さんいませんか?」と編集さんに言われて、そういえば伊波さん、Twitterでよくやり取りしているなと思って名前を出してみたら、お引き受けいただけるということだったので、お礼をして、その流れで飲みましょうかというお話になったんじゃなかったでしょうか。
伊波:そうでした。それで、赤羽で飲んだのでしたね。
高木さんが小説を書きはじめたきっかけ
伊波:高木さんが創作活動を始めたきっかけは、何だったのですか?
高木:もともと漫画の編集者になりたかったんですよ。大学時代に就活で、編集プロダクションとかの存在を知らなかったから、大きな出版社をいくつか受けて受からずに、「編集者になれなかったな」と思ったのですが、じゃあ、自分で書けばいいかと思って、絵の練習をして漫画を描いて、出版社さんに漫画の持ち込みをしていたときがあって。それが何年か続いたんですけど、ある日、編集さんに、「君の漫画は字が多くて読むのがダルい」って言われまして。いまいちパッとしないなと思っていたときに、じゃあ、字だけだったらいけるんじゃないかなと思って小説を書いてみて、書けたものを送ってみたら、賞をいただけて。それが2010年だから、作家になって12年目に入りました。
伊波:もともと小説はお好きなのですか?
高木:そうですね。高校のときに村上春樹さんが好きでずっと読んでいて、あとは、わりと古い日本文学と、大学のときにラテンアメリカ文学にハマって読んでいて、自分がデビュー当時に書いていたライトノベルだとかライトミステリーだとかは、ぜんぜん通ってなかったですね。だけど、漫画雑誌の編集さんに、「高木君、こういう話好きだったら、こういう本を読んだらいいよ」って、米澤穂信さんの『ボトルネック』と山本弘さんの『MM9』と、あと、『涼宮ハルヒの憂鬱』の3冊を紹介していただいて、それで本屋さんに行って探していたら、そういうタイプの本がいっぱいあるんだと気づいて読むようになった感じがありますね。
高木さんが小説を書くときに考えていること
伊波:高木さんは、よく音楽を題材にされていますが、どうしてですか?
高木:2013年に早川書房さんから出した『演奏しない軽音部と4枚のCD』は、変わったCDを題材にした学校が舞台の軽めのミステリーということで書きました。それで音楽のネタを書いてみたら、意外とそれがきっかけで読んでくださる方もいたので、自分の趣味みたいなものをちょこちょこ盛り込んでいくのも楽しそうだと思ったというのもありますね。
伊波:僕が帯文を書かせていただいた、『さよならが言えるその日まで』は特殊な設定でしたが、どうしてそのような形になったのですか?
高木:何を言ってるんだと思うかもしれませんが、わりと僕は夢を鮮明に覚えているほうで、夢のなかで面白かったと思ったものはメモしていることが多くて。あれも、ベースは面白いと思った夢の設定だけメモしてあって、そこから膨らませたんです。
伊波:あの作品は設定も特殊ですが、「家族のカタチ」というテーマもキーになっていました。
高木:僕は最初にカッチリ決めて書くのが苦手で、書いているうちに、「ああ、この話はこういうテーマなんだな」というのが自分でわかってきて、そこを目指していくので、書いているうちに家族の話に着陸するなと思って、そういう方向に進めました。
高木さんの幅広い執筆活動について
伊波:最近は、「現代ビジネス」でエッセイの連載もされていますが、どういった経緯で始まったのですか?
高木:僕と編集さんとの間に、たまたま共通の知り合いがいたんです。で、あるとき引き合わせていただいたら、割とすんなり「ちょっとやってみましょう」という話になりました。
伊波:内容は、毎回どのように決めているんですか?
高木:最初のいくつかは、編集さんとどんなテーマがいいか話をしていて、僕、方向音痴なので、方向音痴で失敗したエピソードはたくさんあるから、そういうテーマでいつか話を書けるんじゃないかという話をして採用されたんです。1回目のときは、ちょうどタイに旅行へ行ってきたところだったので、それについて書きました。2回目は、「高木さんのこれまでのキャリアの迷走について書いてください」となって、方向音痴って、そういう大きな意味だったんだと思いました(笑)。
伊波:最近は児童文学も書かれていますが、一般文芸とは感覚が違いそうですね。
高木:小説を書くときに、「読者層を想定してください」とよく言われるのですが、そこがすごく苦手で。これまでも読者層を漠然とは想定しているけれど、自分以外のことなんてわからないので、顔が見えているかと言われるとそうでもなく、自分のことだったらわかるから、自分だったら好きだなという方向で書いてきました。ただ、これまでの人生を振り返ったときに、自分みたいな人ってそんなに多くはないから、自分みたいな人が手に取りそうな本を書いても、手に取ってくれる人はそんなに多くないんですよね。でも児童文学を書くにあたっては、小学校の頃を思い出すと、朝に読書の時間があったりしたので、教室で小学生が本を開いて読んでいるようなイメージは具体的に見えて。じゃあ、そういうところでサラッと読めて、面白かったなって思ってもらえるようなものをって考えたら、今回の『幽霊お悩み相談室』をスラスラ書くことができました。結果的に、この経験が他でも生かせそうな手応えを感じています。
今後について
伊波:今後は、どういった作品を書いていきたいですか?
高木:基本的に、自分が読みたいものって、読み終わるまで面白いのかどうなのかわからないものだという感じがするんですよね。たとえば、あらすじってすごく苦手で。書店さんとかで、小説の表紙を見て面白そうって思っても、裏返してあらすじを読むと、だんだんイメージが定まってきて、面白そうだと思わなくなってしまうことが多くて。だからあらすじは読まずに買うことがほとんどなんですけど、そういうことを編集さんに言うと、「あらすじとか帯とかはすごく大事で、あれを読んで買ってくださる方がすごく多い」と言われますし、勿論それを否定するつもりはないのですが。ただ、面白いのかどうなのかわからないものが書きたいって言って書かせてくれる人っていないと思うので、そういうものを書いてみてから、知ってる編集さんに読んでいただいて、「よくわからないけれど、読み終わってみたら面白かったよ」って言ってもらえて、結果的に本として出せたりしたらいいなと思っています。
伊波:今回は、ありがとうございました!

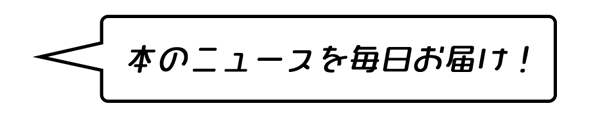




-88x88.jpg)